春の訪れとともに、東京都内には美しい桜が咲き誇ります。
その中でも、観光客があまり気づいていない、隠れスポットを巡ってみませんか?
歴史ある神社の境内で楽しめる、知る人ぞ知る桜の絶景を一挙にご紹介します。
都会の喧騒を忘れ、静かで穏やかなひとときを過ごせる9つの神社。
その魅力と共に、散策のポイントや神社の由緒もお届けします。
靖国神社
靖国神社は、明治2年(1869年)に明治天皇の命により創建された神社です。
国家のために命を捧げた人々の御霊を慰め、その貢献を後世に伝えることを目的としています。
この神社の起源は、明治維新の際に招魂社として設立されたもので、明治12年に「靖国神社」と改名されました。
「靖国」には「国を安んずる」という意味が込められています。
そして、靖国神社といえば、忘れちゃいけないのが桜です。
境内には東京の桜の標本木があり、ソメイヨシノ約500本が咲き誇ります。
桜の時期には「奉納夜桜能」などの催しが行われ、多くの参拝者が訪れます。
神社は九段下駅から徒歩5分の立地で、入場は無料です。
神田明神
神田明神(正式名称・神田神社)は、東京の中心部に位置し、「明神さま」として親しまれている神社です。
創建は天平2年(730年)で、御祭神として国土経営と縁結びの大己貴命、商売繁昌の少彦名命、そして除災の平将門命が祀られています。
神社の歴史は平将門公の御神威から始まり、戦国時代や徳川家康の天下統一にも関連。
江戸時代には幕府の尊崇を受け、「江戸総鎮守」として庶民に愛されました。
関東大震災で被災しましたが、昭和に鉄骨鉄筋コンクリートの社殿が再建。
そのおかげか、戦災にも耐えました。
現在は静かな桜の名所でもあり、3月下旬から4月上旬に見頃を迎えます。
上野東照宮
上野東照宮は、徳川家康を祀る神社で、1627年に創建されました。
東京都台東区の上野公園に位置しています。
ご利益は、出世、勝利、健康長寿などです。
神社の豪華な建造物は戦争や地震を経ても崩壊を免れ、国の重要文化財として保護されています。
参道には桜並木があり、春には多くの桜が咲き誇り、幻想的な景観を作り出します。
この美しい景色は、日本人だけでなく海外観光客からも人気です。
五重塔の夜のライトアップと桜の共演は古き良き日本を思わせます。
明治神宮外苑
明治神宮外苑は、1926年に完成した東京都新宿区と港区にまたがるスポーツ・文化施設や公園を含むエリアです。
このエリアは、明治神宮が66.2%を保有し管理しています。
戦後、GHQに接収されたものの1952年に返還され、現在は聖徳記念絵画館や明治神宮野球場、秩父宮ラグビー場がある施設として親しまれています。
特に有名なのがイチョウ並木と、約310本の桜が並ぶ風景です。
桜はソメイヨシノやシダレザクラなどが楽しめ、例年3月下旬から4月上旬に見頃を迎えます。
大宮八幡宮
大宮八幡宮は、第70代後冷泉天皇の時代に、源頼義が奥州の乱を鎮めるために創建を誓った神社です。
1063年に創建され、「多摩の大宮」や「武蔵国八幡一之宮」とも呼ばれていました。
ここでは応神天皇を主祭神としており、ご利益は厄除け、縁結び、安産、子育て、交通安全などです。
毎年4月には大宮八幡宮周辺の和田堀公園で「大宮八幡 桜まつり」が開催され、夜間参拝が可能になり、幻想的な夜桜が楽しめます。
桜神宮
桜神宮は、1883年に古式神道を復興するために創建され、1919年に現在の場所へ移転しました。
主祭神の天照大御神を祀り、通常の二拝二拍手一拝ではなく、二拝四拍手一拝の拝礼作法が特徴です。
世田谷区の「お伊勢さん」として親しまれ、桜新町駅から徒歩数分の場所にあります。
桜神宮は河津桜、しだれ桜、ソメイヨシノなど多様な桜が楽しめ、特に3月上旬が見ごろ。
花帯の習慣や桜モチーフの御守りなども人気です。
桜並木は桜新町の由来で、4月中旬にも八重桜が楽しめます。
大國魂神社
大國魂神社は、大國魂大神を祀る武蔵国の神社です。
出雲の大国主神と同じ神とされ、福神や縁結び、厄除けの神として知られます。
神社内は桜の名所で、大鳥居付近のソメイヨシノや随神門周囲の枝垂れ桜が見事です。
特に神楽殿前の枝垂れ桜は明治100年にロータリークラブから寄贈されたもので、多くの市民に親しまれています。
平成28年には、新たに八重紅枝垂れ桜も植樹。
4月にかけて長く桜を楽しむことができます。
愛宕神社(港区)
愛宕神社は1603年、徳川家康により防火の神として祀られ、幕府からの厚い尊崇を受けました。
江戸の大火災や関東大震災、東京大空襲で何度も焼失しましたが、昭和33年に再建。
標高26メートルの愛宕山頂に位置し、春には桜、夏は木々の涼、秋の紅葉、冬の雪景色など四季折々の美しさがあります。
オフィス街のオアシスとして近隣で働く人々に安らぎを提供。
周辺の桜も見応えがあります。
筑土八幡神社
筑土八幡神社は、東京都新宿区に位置する神社です。
江戸時代までは筑土八幡宮と呼ばれていました。
嵯峨天皇の時代に、八幡神のお告げにより祀られたのが起源とされています。
円仁が祠を建て、最澄作とされる阿弥陀如来像を安置しました。
1469年から1487年の間に上杉朝興により社殿が建設。
鎮守として祀られました。
1945年の戦災で焼失しましたが、現在も当地にあります。
参道にはトンネルのように桜が咲き誇り、桜の名所としても人気のスポットです。
まとめ
この記事では、東京都内の桜の名所として、観光客にはあまり知られていない神社を紹介しました。
以下はそれぞれの神社の特徴をまとめたものです。
- 靖国神社:
- 明治2年(1869年)に創建
- ソメイヨシノ約500本が美しく咲く
- 奉納夜桜能などのイベントが開催
- 神田明神:
- 創建は天平2年(730年)
- 桜の見頃は3月下旬から4月上旬
- 歴史的な背景を持つ重要な神社
- 上野東照宮:
- 徳川家康を祀る神社
- 豪華な建造物と桜並木がある
- 夜には五重塔のライトアップと桜が幻想的な景観を創出
- 明治神宮外苑:
- 約310本の桜を楽しめる
- ソメイヨシノやシダレザクラが見頃を迎える
- 大宮八幡宮:
- 「多摩の大宮」とも呼ばれる
- 4月には桜まつりが開催
- 夜桜も楽しめる
- 桜神宮:
- 多様な桜を楽しめる
- 特に河津桜が有名
- 桜新町の由来ともなっている
- 大國魂神社:
- 武蔵国の神社
- ソメイヨシノと枝垂れ桜が見事
- 愛宕神社(港区):
- 標高26メートルの愛宕山頂に位置
- 季節ごとの景観が楽しめる
- 筑土八幡神社:
- 参道の桜がトンネルのように咲き誇る
- 桜の名所として広く知られている
以上です。
これらの神社は、都内における静かで穏やかな桜の観賞スポット。
都会の喧騒を忘れてリラックスした時間を過ごしましょう。

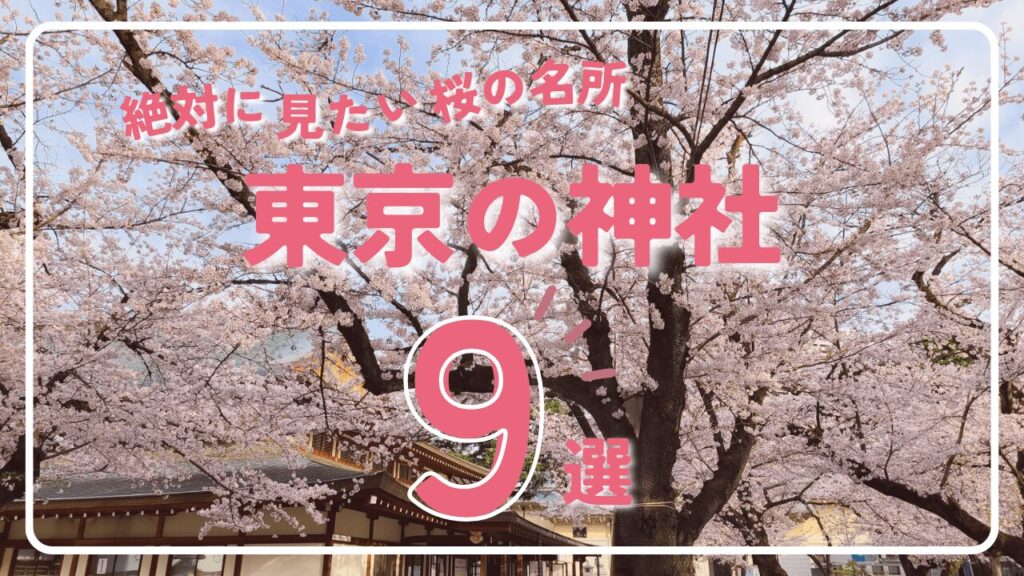

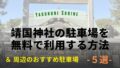
コメント